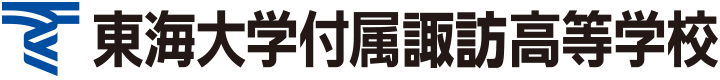「歩く宝石」と呼ばれるアカスジキンカメムシの最終幼齢態(第5齢)
キャンパス周辺の農地では田植えや野菜の苗の移植が始まっています。
さて、これから梅雨に入るとカメムシ類も成長期を迎えます。気が付くといつの間にか壁を這っていたり、洗濯物にくっついていたり、農作物にも害を与えるカメムシですが、その仲間には「歩く宝石」と呼ばれるものがいます。キンカメムシ科のアカスジキンカメムシです。
キンカメムシ科のカメムシは、だいたいにおいて赤や緑、華やかなもの、金属光沢をもつものなど、派手な体色があり、採集化の目をひきます。ただし、死ぬとその輝きが失われ、生きている時とはまるで別の昆虫であるかのように色褪せてしまいます。アカスジキンカメムシの成虫は全体が光沢のある金緑色で、淡い紅色の帯紋が特徴です。その美しさのゆえに宝石にたとえられているのですが、実はその美しさは、生きている間しか見ることができません。言い換えれば、その美しさは生命の輝きゆえのものなのです。
写真は、風に吹かれて裏返しになったクローバーにしがみついているアカスジキンカメが「宝石」になる直前の幼虫時代の姿(5齢)です。
特に3齢以前の体色は「絢爛」という形容がぴったりな輝くメタリック色です。4齢では黒地に赤の帯が入り、5齢になると写真のように白と黒をベースにした落ち着いた体色になります。これから、数日後には朱と緑を基調にした美しい成虫に生まれ変わります。
生命を輝かせるがゆえに体色が美しいアカスジキンカメムシ。美しさの源は生きることだと教えてくれているようです。